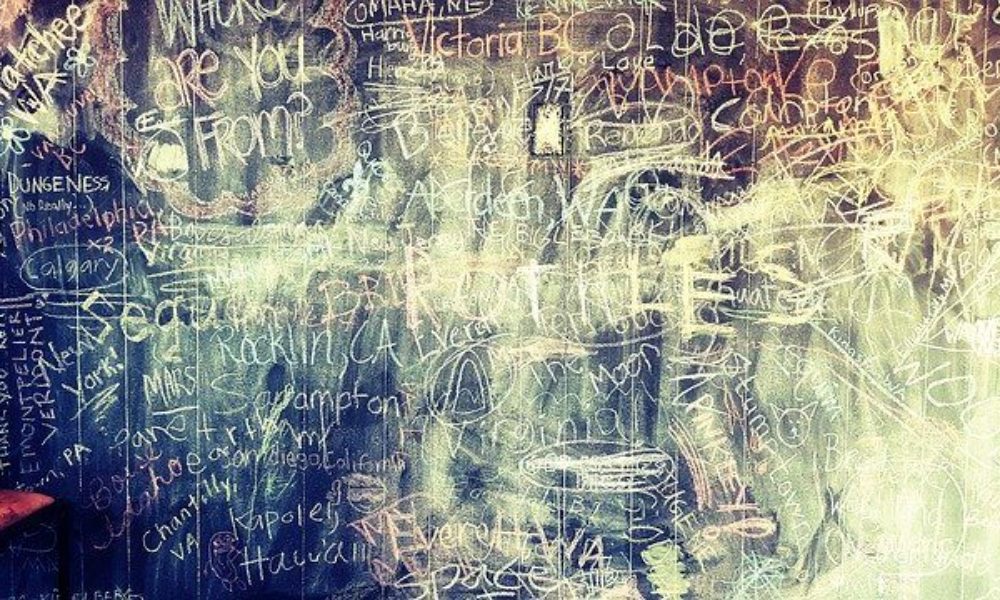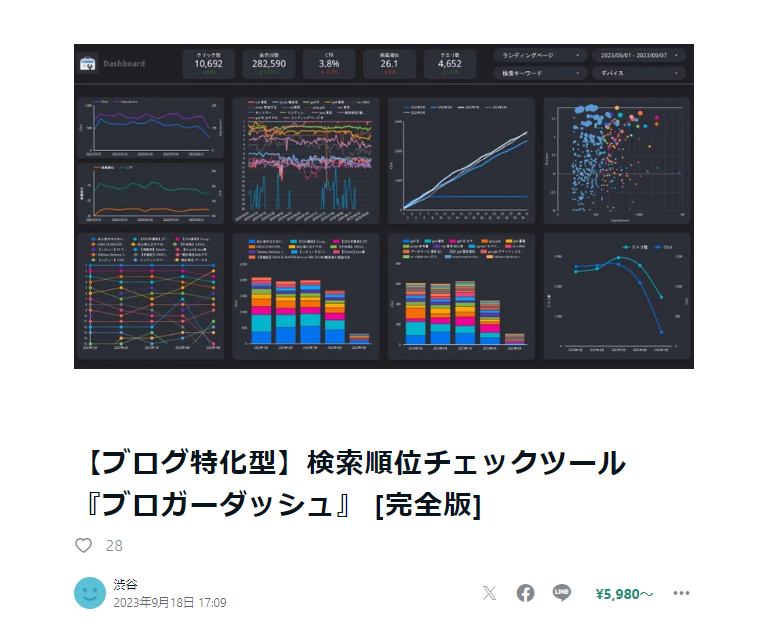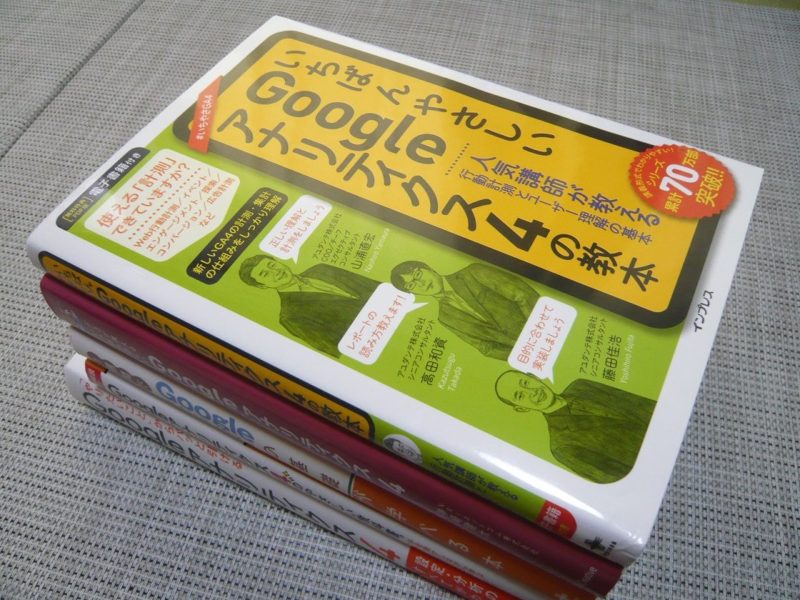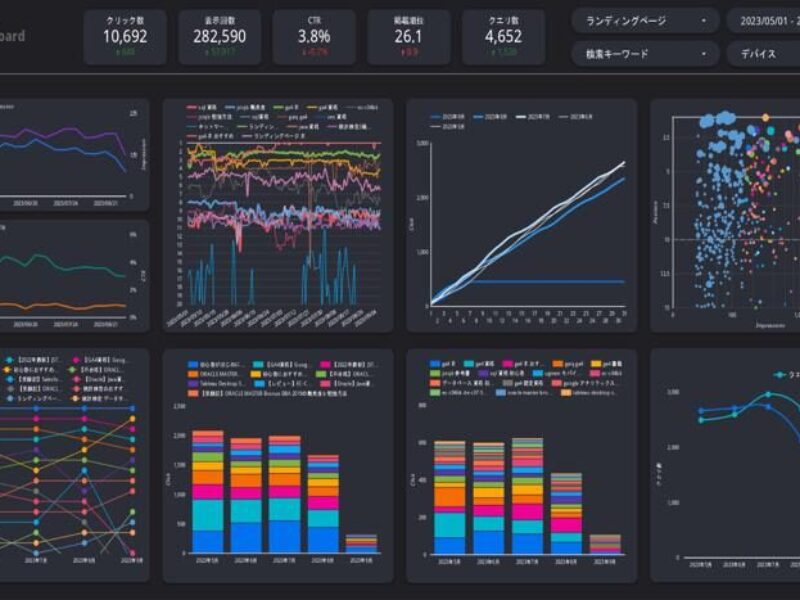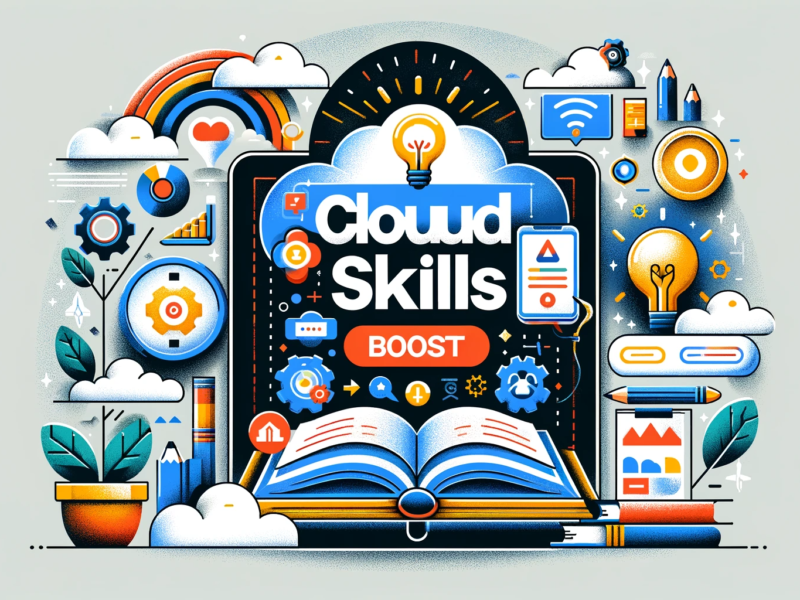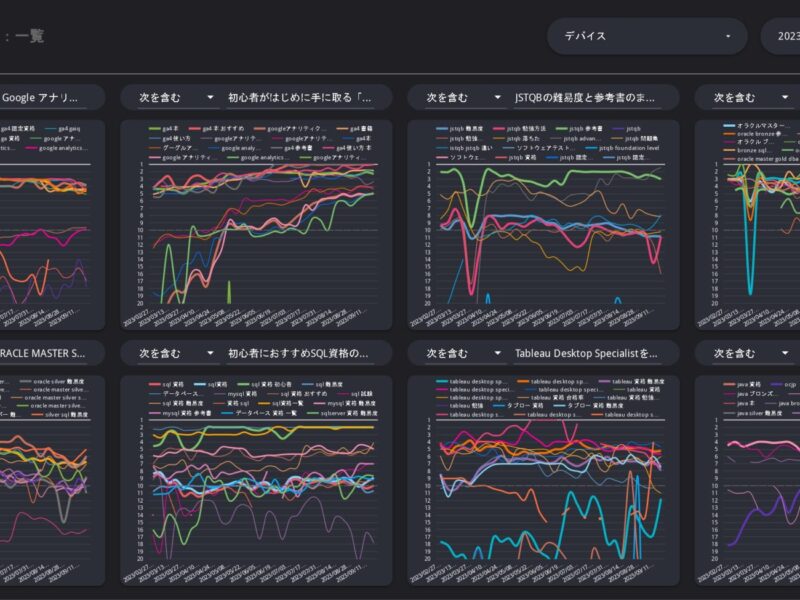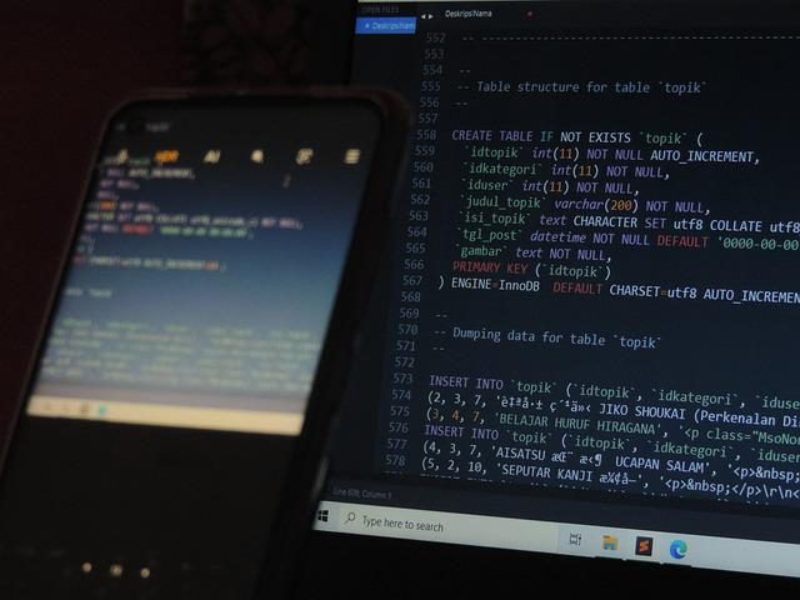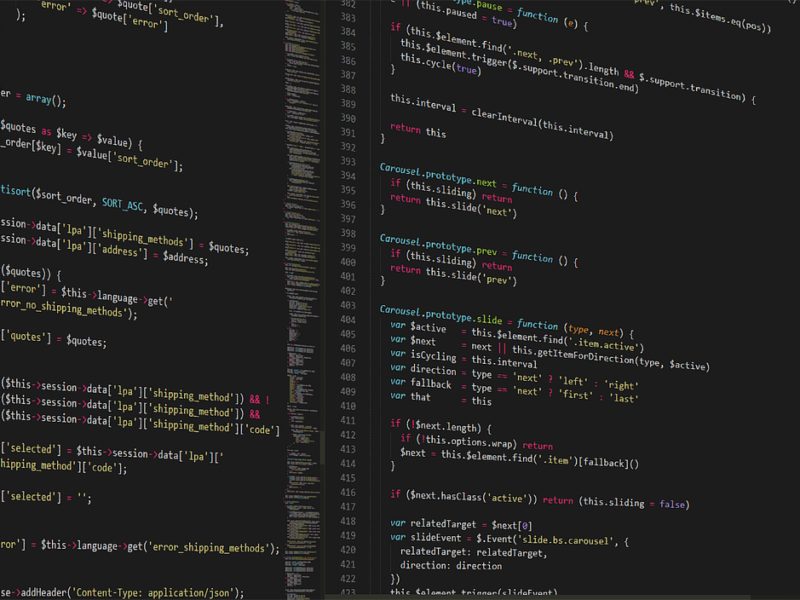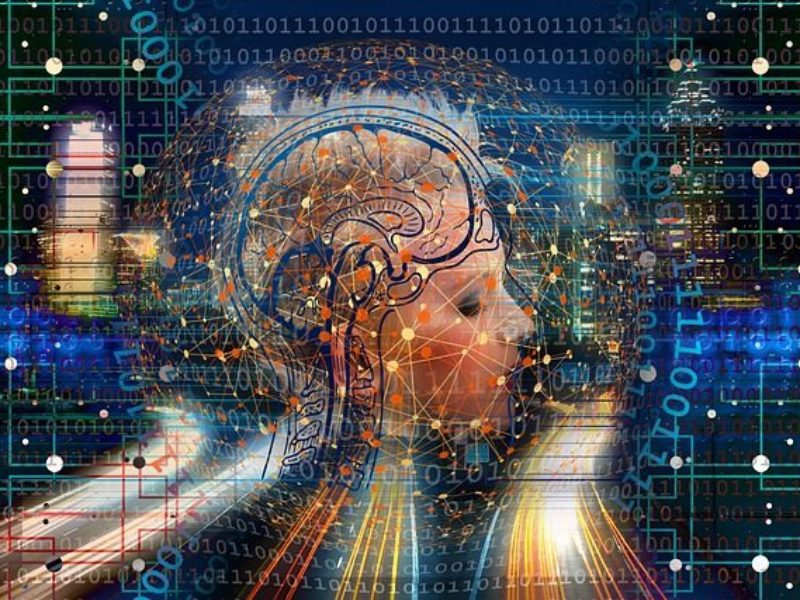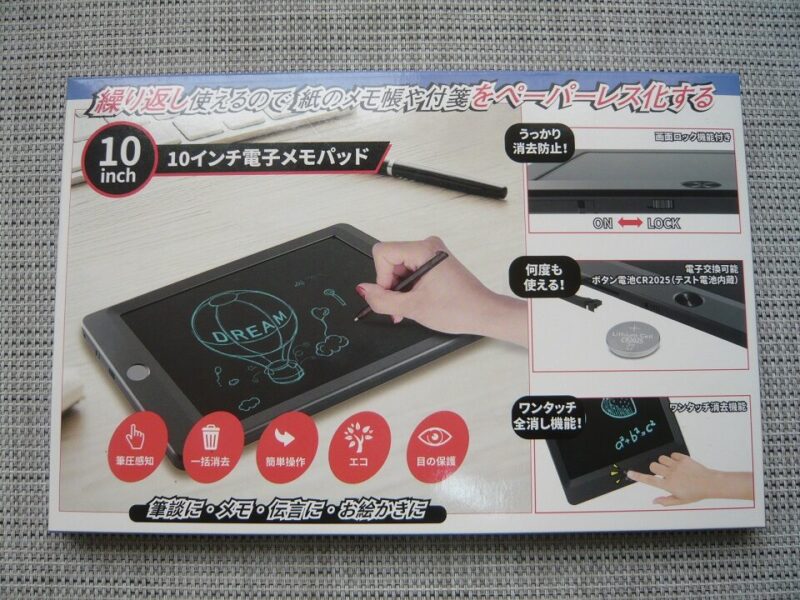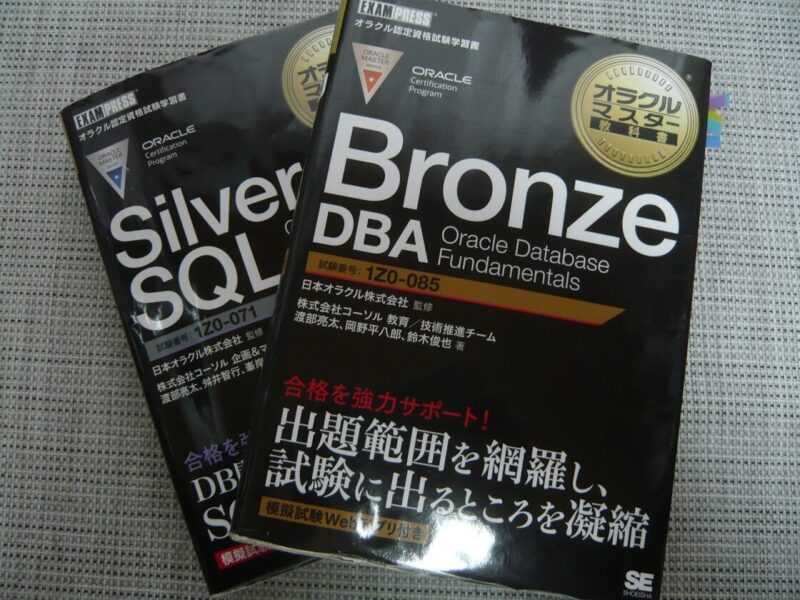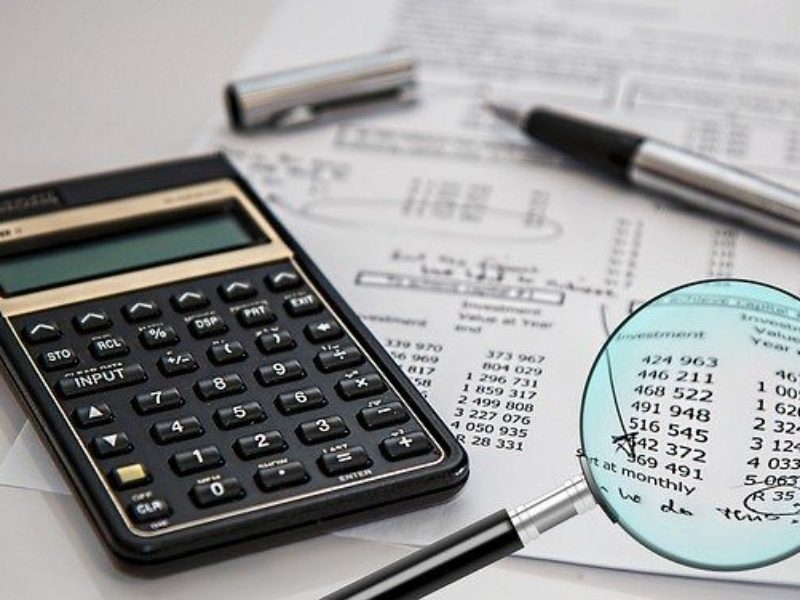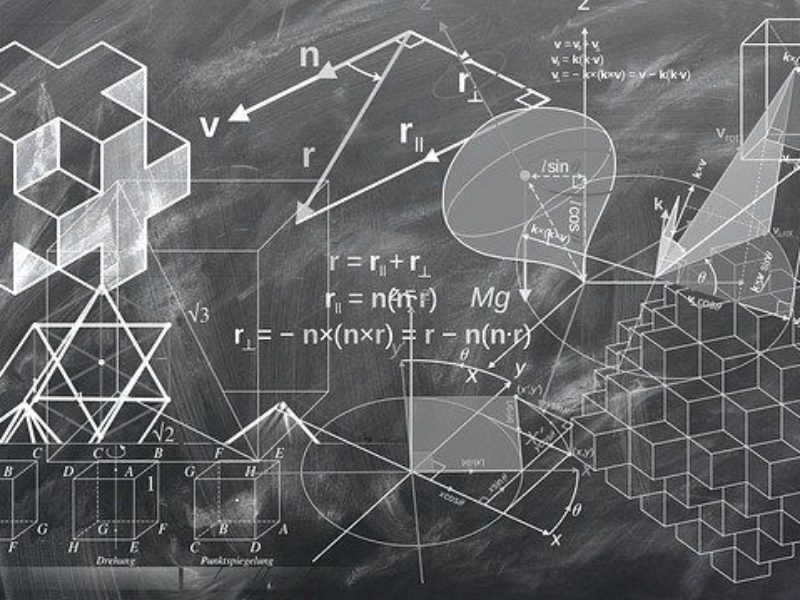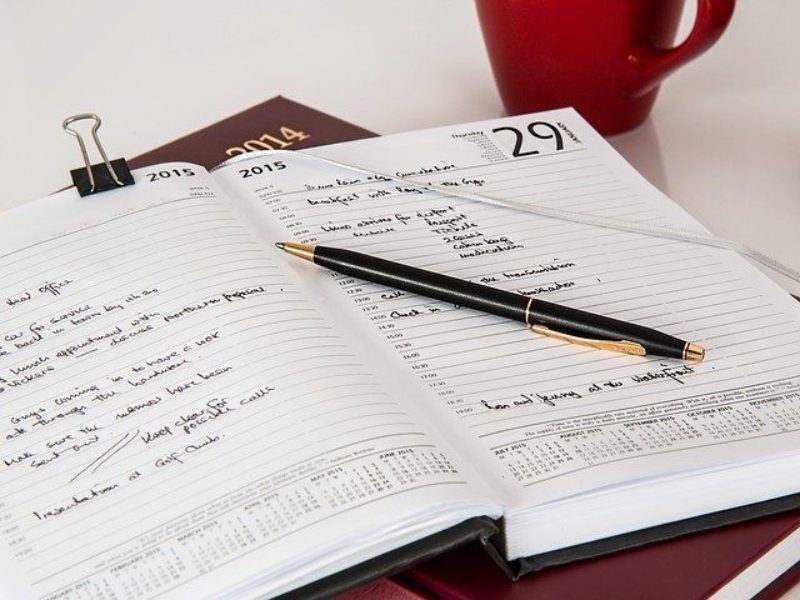始めに結論を提示するが、部分一致とは、ユーザーがGoogle検索で検索をかけたキーワード(検索クエリ)と、その前後で検索をかけたキーワードが部分一致の広告掲載対象となるマッチタイプ。分かりやすく簡潔に説明するとこういうこと↓
「A」というキーワードを[部分一致]で登録する。佐藤さんが「A」を検索すると、広告が表示される。直後に「B」を検索する。すると「B」は「A」と関連性があるとシステムに見なされる。後日、鈴木さんが「B」を検索する。「B」は「A」と関連性があると見なされているので、広告が表示される。ゆえに「B」のキーワードは確度が高いことになる。
これについて詳しく後述するが、巷でよく言われる「関連語や類義語を拾ってくれるのが部分一致」という説明がよくされるが正しい解釈とはいえない。なぜなら、部分一致は辞書的な意味合いで関連語や類義語を判断していないから。これは結果的にそうなることがあるといえるくらいであって、この第一段目の解釈が間違っているから、Google広告の持つ力を引き出せないアカウントが出来上がる。もう一度、重要なことなので言うけど、関連語や類義語を拾うのが部分一致ではない。よく毎度の如く「部分一致は類義語・関連語を拾う」とか言う人がいるけど、なんも分かってねーな、こいつって思う。めんどくせーからいちいち説明しないけど。
部分一致について、ネットや本も含めて解説された記事は、ヘルプページ読んだことあんのか?って思うほど、あまりにもレベルが低く参考にならないし、むしろ成果を落とすことにつながる。なぜなら根本的に土台が間違っているから。間違った解釈の上で構築されたアカウントは成果は出せない。
これから解説することは、他では触れていない部分一致の解釈として非常に価値があり、これを理解することでアカウント構成の組み方が全く変わり、成果を大幅に改善できる部分一致の思考になる。
とはいっても、私はGoogle広告を開発している中の人ではないので、これから述べることは、いってみれば「推測」である。こういった推測はSEOではよくなされる議論であり真相は分からないが、経験則に基づくものであるので大方当たっていることが多い。
思うにGoogleは部分一致というマッチタイプに相当に力を入れていて、今後もキーワード広告の要は部分一致になるだろう。最終的にはキーワードレスを目指していると思うが、検索キーワードがリスティング広告の要である限り、「構文の一致」から外れた部分一致は、今後もマッチタイプの主要な選択肢になり続ける。
部分一致で、なぜその検索クエリに広告が表示されたのか?
つまり、理解すべき点は、なぜその検索クエリに対して、その部分一致が反応したか?の仕組みを知ることである。
判断材料
部分一致で登録したキーワードが、どのような検索クエリに反応するかどうかは、ユーザーが検索をかけたその前後の検索クエリをGoogleは収集していて、これらの検索クエリがまず部分一致の関連性が高いキーワードとして候補に挙がる。そして、関連性が高いと判断されれば、そのクエリは部分一致の広告掲載対象となり、関連性が低いと判断されれば、部分一致として関連性の低いキーワードとして除外されるため広告掲載対象とはならない。
関連性を高さを計る上で最も重要視されているのは、検索キーワードの前後に検索されたキーワード。そしてそのタイムスパンの短さ。例えば「A」を検索し、その直後に「B」を検索し、3日後に「C」を検索した場合、「A」と関連性があるとみなされるのは「B」
また、遷移先のサイトからも関連性があるかの判断材料になるので活用していると想定できる。「A」を検索して遷移したサイトと、「B」を検索して遷移したサイトが全くジャンルが異なるのであれば、「A」と「B」の検索のタイムスパンがたとえ短くとも関連性があるキーワードとはみなされないだろう。
以上で述べた、たぶんこーなんじゃねーかなという推測は、ヘルプページにも記載があるので、たぶん当たっている。
検証
これらの分析を検証するために様々な方法をGoogleは取り入れているはずであり、例えば以下のようなプログラムが組まれていると推測できる。
・検索母数
→「A」の検索の前後には「B」の検索が多く「C」の検索が少なければ、関連性がより強いとみなされるのは「B」
・クリック率
→「A」の検索に関連性があるとみなされた「D」と「E」があったとすると、それぞれ広告が表示された際のクリック率を検証している。仮に「E」の検索時には、著しくクリック率が低い、もしくはクリックされないのであれば、「E」は関連性がない検索クエリとして、部分一致の表示対象から外れる。
意味による一致と構文による一致
このような検索クエリの関連性に基づいて広告表示される部分一致は「意味による一致」と呼ばれる。
| 意味による一致 | 構文による一致 | |
| 完全一致・部分一致 | ◯ | |
| 絞り込み部分一致・フレーズ一致 | ◯ |
部分一致で選択するキーワード
以上の点を踏まえれば部分一致で登録するべきキーワードが見えてくる。それは以下の2つの条件を満たすこと。
・検索需要が多い
・CVが獲得できているキーワード
要はCVが獲得できているキーワードを部分一致で登録することは、CVの獲得につながった可能性の高い検索クエリの前後にかけられた検索クエリにアプローチできることを意味する。また、精度を上げるためには、検索需要が多いキーワードを登録する。検索需要が多いほど、その検索クエリの意味による一致の分析が進んでいるためターゲティングの確度が高くなるから。
結論
部分一致が完全一致や絞り込み部分一致と大きく異なる点は、自然検索やリスティング広告から得られた、これまでの膨大な検索クエリを分析した結果を活かせること。なので全く関連語や類義語ではないクエリに反応することがあるし、それは検索キーワードの前後のキーワードであるため、一見すると関連性はないようにみえるかもしれないが、関連性はある。
まとめていえば、部分一致で登録したキーワード、つまりこれは実際に検索された検索キーワード(検索クエリ)と同義となり、部分一致で拾いあげる検索クエリは、この登録キーワードの前後で検索された検索クエリが部分一致で反応する。つまり、登録キーワードによって拾いあげる検索クエリは変化するということ。
既に削除されてしまったがGoogle広告の公式ヘルプページに以下の記載があった。
狙いたい検索意図を定めて、その回答を返すであろう検索需要があるキーワードを登録する。
≫ Google 広告 ヘルプ -関連リンク-
・部分一致とは
・部分一致を使用する
・成果拡大と管理性向上に向けたマッチタイプの活用